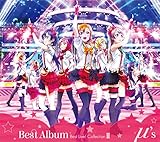DMC−G1とマイクロフォーサーズが見せる未来。
久々にデジカメ関連のひとりごとなど。
従来のフォーサーズ規格をさらに小型化したマイクロフォーサーズが発表されたのが先月の事。
オリンパスを中心に立ち上げられたフォーサーズは、二つの泣き所を抱えていました。
ひとつはイメージサークルの小ささからくる、ファインダー像の小ささ。
もうひとつは、厳密にはフォーサーズの欠点ではないけど、フィルム時代にAF化に乗り遅れたオリンパスは他社に比べてAF技術が遅れている事。
これらの欠点を克服する方法は、背面液晶によるライブビューとEVFに移行する事。
イメージサークルの大きさに左右される光学式ファインダーを廃止し、液晶に表示させればファインダー像はいくらでも大きくできるし、視野率100%も低コストに実現できます。
AF技術の遅れも、コントラストAFを他社に先駆けて開発する事で、むしろアドバンテージに変える事ができます。
この事を考えると、ミラーボックスを廃止してライブビューとEVFに切り替え、小型軽量化を狙ったマイクロフォーサーズが登場するのは、当然の事と言えます。
……問題は、この事をマイクロフォーサーズの発表前に書いておけば良かったのに、という事。
それはさておき、マイクロフォーサーズに準拠した最初の製品として発表されたのが、パナソニックのDMC−G1です。
マイクロフォーサーズならではの小型軽量ボディに、高精細EVFとフリーアングル液晶と高速化したコントラストAFを搭載。
ボディカラーもオーソドックスなコンフォートブラックの他に、コンフォートレッド、コンフォートブルーの三色を用意し、女性を中心とした新しいユーザー層の開拓を狙う構えです。
実機を触っていないので想像だけで書くけど、軽量コンパクトで不満なく使えそうな印象です。
だけど個人的には疑問を感じる部分もあります。
軽いと言っても、実はオリンパスのE−410やE−420に比べると、ほんの少しだけ重いのです。
もちろんDMC−G1はフリーアングル液晶だから、などの言い訳はできるかと思いますが、新しいマイクロフォーサーズの第1弾と考えれば、もっと大胆な方向性も考えられたのではないでしょうか?
背面液晶もフリーアングルである必要性はないし、EVFも絶対に必要とは思えません。
それらがあった方が便利かも知れませんが、あえてそれらをなくして、マイクロフォーサーズらしさを突き詰めた方が、第1弾としては相応しかったのではないでしょうか?
誤解されないように書くけど、DMC−G1が悪いカメラだと貶めるつもりはありません。
過不足なく使えたとしても、他よりちょっと小さいだけのカメラより、多少不便でも、あり得ないくらい小さいカメラの方が、マイクロフォーサーズの第1弾としては相応しいんじゃないかと思うわけで。
いずれ近い将来、第2弾か第3弾として、マイクロフォーサーズでは一番大きい機種、として登場するべきだったんじゃないかと。
ミラーボックスを廃止したDMC−G1は、確かにデジカメの未来を予感させてくれます。
でも、まだ未来その物とは言えないんじゃないでしょうか。
そんな気がします。
でわでわ。
この記事の評価をして下さい。
従来のフォーサーズ規格をさらに小型化したマイクロフォーサーズが発表されたのが先月の事。
オリンパスを中心に立ち上げられたフォーサーズは、二つの泣き所を抱えていました。
ひとつはイメージサークルの小ささからくる、ファインダー像の小ささ。
もうひとつは、厳密にはフォーサーズの欠点ではないけど、フィルム時代にAF化に乗り遅れたオリンパスは他社に比べてAF技術が遅れている事。
これらの欠点を克服する方法は、背面液晶によるライブビューとEVFに移行する事。
イメージサークルの大きさに左右される光学式ファインダーを廃止し、液晶に表示させればファインダー像はいくらでも大きくできるし、視野率100%も低コストに実現できます。
AF技術の遅れも、コントラストAFを他社に先駆けて開発する事で、むしろアドバンテージに変える事ができます。
この事を考えると、ミラーボックスを廃止してライブビューとEVFに切り替え、小型軽量化を狙ったマイクロフォーサーズが登場するのは、当然の事と言えます。
……問題は、この事をマイクロフォーサーズの発表前に書いておけば良かったのに、という事。
それはさておき、マイクロフォーサーズに準拠した最初の製品として発表されたのが、パナソニックのDMC−G1です。
マイクロフォーサーズならではの小型軽量ボディに、高精細EVFとフリーアングル液晶と高速化したコントラストAFを搭載。
ボディカラーもオーソドックスなコンフォートブラックの他に、コンフォートレッド、コンフォートブルーの三色を用意し、女性を中心とした新しいユーザー層の開拓を狙う構えです。
実機を触っていないので想像だけで書くけど、軽量コンパクトで不満なく使えそうな印象です。
だけど個人的には疑問を感じる部分もあります。
軽いと言っても、実はオリンパスのE−410やE−420に比べると、ほんの少しだけ重いのです。
もちろんDMC−G1はフリーアングル液晶だから、などの言い訳はできるかと思いますが、新しいマイクロフォーサーズの第1弾と考えれば、もっと大胆な方向性も考えられたのではないでしょうか?
背面液晶もフリーアングルである必要性はないし、EVFも絶対に必要とは思えません。
それらがあった方が便利かも知れませんが、あえてそれらをなくして、マイクロフォーサーズらしさを突き詰めた方が、第1弾としては相応しかったのではないでしょうか?
誤解されないように書くけど、DMC−G1が悪いカメラだと貶めるつもりはありません。
過不足なく使えたとしても、他よりちょっと小さいだけのカメラより、多少不便でも、あり得ないくらい小さいカメラの方が、マイクロフォーサーズの第1弾としては相応しいんじゃないかと思うわけで。
いずれ近い将来、第2弾か第3弾として、マイクロフォーサーズでは一番大きい機種、として登場するべきだったんじゃないかと。
ミラーボックスを廃止したDMC−G1は、確かにデジカメの未来を予感させてくれます。
でも、まだ未来その物とは言えないんじゃないでしょうか。
そんな気がします。
でわでわ。